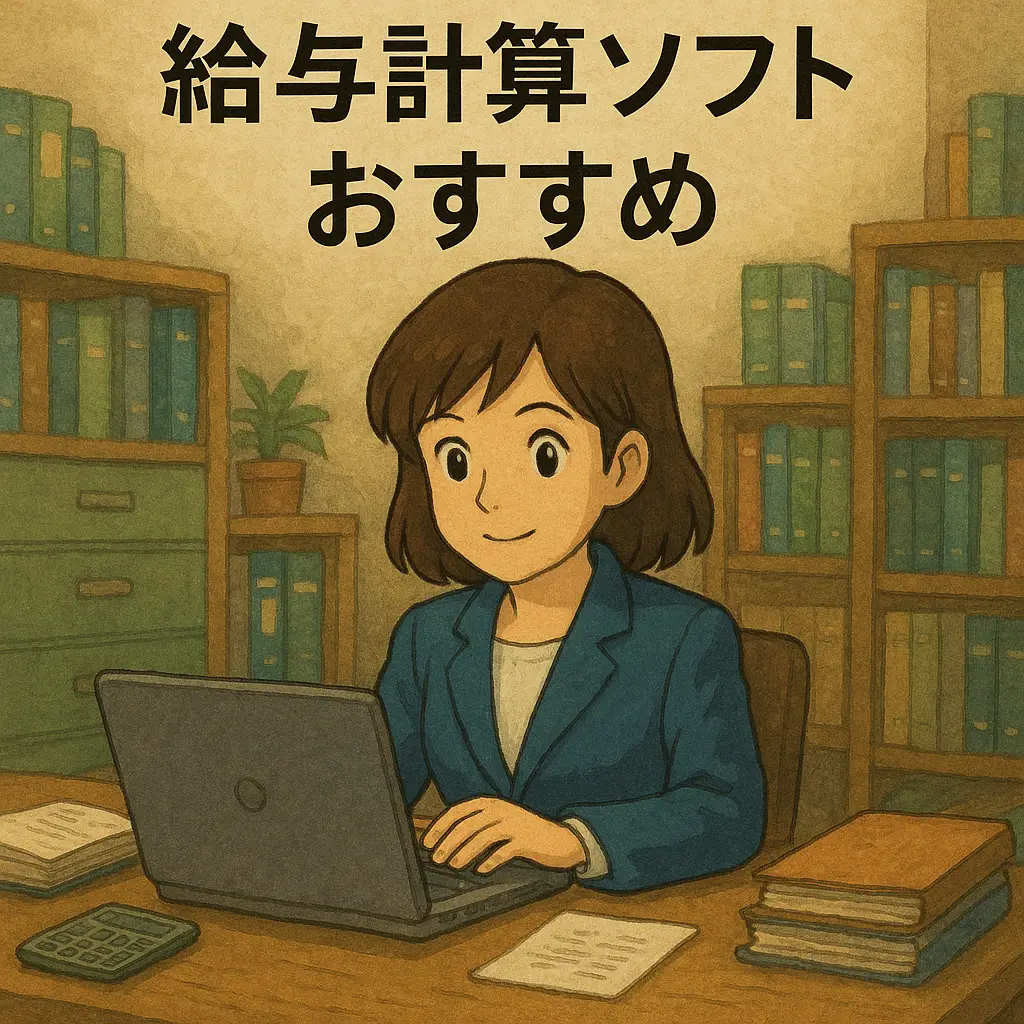人事労務の工数削減を目的とするなら、下表の5つから選べば、大失敗はしないでしょう。
| ソフト名 | 電子申請 | 勤怠連携 | 会計連携 | 導入実績 | 最適な規模 |
|---|---|---|---|---|---|
| freee人事労務 | 62万事業所 | 1〜30名 | |||
| マネーフォワード給与 | 中小企業多数 | 5〜100名 | |||
| ジョブカン給与 | 25万社 | 1〜50名 | |||
| SmartHR | 大企業・中堅多数 | 30〜300名 | |||
| 弥生給与 | 小規模企業に強い | 10〜50名 |
給与計算は、勤怠管理・社会保険・年末調整・会計仕訳と密接に関わるため、「自動化の強さ」と「電子申請の対応範囲」が最も重要です。
2025年執筆時点で、実務の安定性と自動化性能で信頼できるのは上表の5つです。
- freee人事労務:一人社長・少人数企業の最適解
- マネーフォワードクラウド給与:会計連携最強
- ジョブカン給与計算:勤怠連携に圧倒的強み
- SmartHR(給与オプション):人事領域全体をDX
- 弥生給与:オフライン+安定運用の定番
本記事では、これら5つを、人事担当者・一人社長が“本当に知りたいポイントだけ”に絞って比較します。
なお、私は無料の給与計算ソフトをおすすめしていません。
なぜなら、機能が限定されており、電子申請・勤怠連携・年末調整といった必須業務が結局手作業になるからです。
その結果、人為的ミスのリスクが高く、実務負担も減りません。
また、法令改正への対応が遅れやすく、サポート体制も十分ではありません。
給与計算は誤りが許されない領域であるため、無料ツールは業務品質と安全性の観点から、有料サービスを使うのが安全です。
太田昌明(公認会計士・税理士)
2014年 EY新日本有限責任監査法人 入所
2021年 ニューラルグループ株式会社 入社
2022年 株式会社フォーカスチャネル取締役 就任
2024年 太田昌明公認会計士事務所 開業
2024年 太田昌明税理士事務所 開業
2024年 ARMS会計株式会社 設立
2025年 東京税理士会向島支部 幹事(役員)【税務支援対策部】
給与計算ソフトを選ぶ際に人事・経営者が重視すべき3つだけ
給与計算ソフトを選択するには、以下の視点が重要です。
- 勤怠との連携ができるか
- 電子申請に対応しているか
- 会計ソフトとの連携があるか(MF/弥生/freeeなど)
- 年末調整がスムーズか
- 従業員数に適した料金体系か
その中でも、特に重要なポイント3点を解説します。
電子申請が強いか(算定・月変・労働保険)
ここが弱いソフトは、人事部にも一人社長にも負担が残り続けます。
その点、「freee」「SmartHR」「マネーフォワード」 は電子申請に強いラインナップです。
勤怠・会計との連携(手入力ゼロ化が可能か)
給与の数字は勤怠と会計に二重で使うため、連携が弱いと毎月手入力が発生します。
この点、「freee」「ジョブカン」「マネーフォワード」 が特に優秀だと思います。
導入実績と安定性(トラブルの少なさ)
給与計算は障害が出ると即トラブルになるため、運用実績が重要です。
SmartHR・freee・マネーフォワードは特に安心感が高いです。
給与計算ソフトは「freee」「マネーフォワード」「弥生」の三強から選べば間違いない
給与計算は法令改正・社会保険・年末調整など、専門知識が必要な領域であり、手作業で行うにはリスクが高い業務です。
(参考:『税制改正による年末調整の変更点と注意点について』)
2025年の執筆時点で、機能・価格・使いやすさを総合的に評価すると、以下の3社が最も安定しています。
- freee人事労務:初心者・個人事業主向け。自動化の完成度が高い
- マネーフォワードクラウド給与:会計ソフトとの連携を重視する法人向け
- 弥生給与:従来型の操作性と安定感を求める中小企業向け
給与計算ソフトを導入すべき理由
給与計算ソフトには、単なる業務効率化を超えたメリットがあります。
法令改正への自動対応
社会保険料率、源泉所得税、年末調整の変更など、毎年更新が発生します。
ソフトであれば自動アップデートされ、人為的ミスを防げます。
社会保険・労働保険の書類作成を自動化
算定基礎届、月額変更届、労働保険年度更新の書類を自動作成でき、提出までスムーズです。
会計ソフト・勤怠ソフトとの連携
手入力をなくし、締め作業を短縮できます。
ミス削減と同時に内部統制面でも有効です。
人件費の可視化
給与台帳や部門別人件費を自動で集計でき、中小企業の経営判断に活用できます。
おすすめ給与計算ソフト5選(2025年執筆時点)
freee人事労務
一人社長・少人数企業に最も適しています。「勤怠→給与→会計→社会保険手続」がほぼ自動で流れるため、手間がかかりません。
- 電子申請対応に強い
- freee会計と連携
- 初任者でも迷わないUI
向いている規模
1〜30名の企業・個人事業主(法人化直後にも最適)
マネーフォワードクラウド給与
会計との連携が最も正確で分かりやすく、数字管理を重視する会社に最適です。
- 会計・経費・勤怠との連携精度が高い
- 人事労務全体をクラウド上で統一できる
- 申請書類の自動作成が強い
向いている規模
5〜100名の中小企業
ジョブカン給与計算
ジョブカン給与計算は、勤怠管理システムとして高いシェアを持つ「ジョブカン勤怠」との連携力が最大の特徴です。
勤怠データを自動で取り込み、給与計算まで一気通貫で処理できるため、一人社長やバックオフィス専任者がいない企業でも運用負担を大幅に軽減できます。
UIがシンプルで操作性が高く、給与明細の電子配布も標準装備されているため、従業員数が増えても運用が煩雑になりません。
- ジョブカン勤怠と自動でデータ連携
- UIが非常にシンプル
- 導入企業25万社超の安心感
向いている規模
1〜50名の企業(特にジョブカン勤怠利用中の会社)
SmartHR
評価・入退社・契約管理まで、人事の頭痛ポイントを一元化できるのが特徴です。
「SmartHR(給与計算)」では、登録済みの従業員データがそのまま給与計算機能に反映されるため、データ入力や転記作業を大幅に削減できます。
給与計算に必要な履歴情報まで含めた従業員データベースが最新の状態で連携されるので、CSVの取り込みや二重入力によるミスのリスクを抑えられます。
さらに、チェック機能では「特定の条件に該当する従業員だけを絞り込み、必要な項目だけ確認できる」ため、膨大な給与データの中でも効率的に精査が可能です。
計算結果を基にして給与明細や源泉徴収票を画面上から簡単に作成・配付でき、紙明細や手作業での配布に伴う手間も削減されます。
年末調整・社会保険届出ともスムーズに連携し、給与業務をワンストップで効率化できる点も、人事部・一人社長いずれにも大きな魅力です。
- 入退社手続き、文書配布が圧倒的に便利
- 社員情報データベースが強い
- 給与以外の人事DXに効く
向いている規模
30〜300名(人数が増えるほど価値が上がる)
弥生給与
「弥生給与」は、給与・賞与・年末調整・社会保険といった一連の給与業務を一つのパッケージでスムーズに処理できる点です。
勤怠データや従業員マスタから支給額・控除額・保険料を自動で計算でき、給与明細のWeb配信やFBデータ出力による一括振込対応も可能で、手作業の転記ミスや封入印刷などの手間を大幅に削減できます。
また、クラウド版「弥生給与 Next」では勤怠・労務管理機能も追加され、給与業務のみならず入退社手続き・社会保険提出などの労務ワークフローまで一元化されているため、一人社長や人事部が少人数の企業でも安心して運用できます。
さらに、最新の法令改正があった際も自動アップデート対応されているため、税制・保険料率の変更によるリスクを低減可能です。
経理・労務の担当者が多くない環境でも、運用負荷を抑えつつ堅実な給与業務体制を整えたいと考える企業にとって、有力な選択肢と言えます。
向いている規模
10〜50名の小規模企業
無料で使える給与計算ソフトはあるか?
freee人事労務は3名まで無料で利用することが可能であり、一番おすすめです。
それ以外にも無料で使える給与計算ソフトは存在しますが、一人社長や人事部の方にとって「完全無料=導入して安心」というわけではなく、注意すべき制限や運用リスクがあります。
例えば、フリーウェイ給与計算 は「従業員5名までなら永久無料」で利用可能、年末調整・社会保険料の自動計算・給与明細メール送信など基本機能が備わっています。
また、ジョブカン給与計算 も無料プランを用意しており、従業員5名以内であれば費用をかけずに導入可能です。
ただし、無料プランには、例えば次のような制限があることを認識しておく必要があります。
- 従業員数上限
- 機能制限(年末調整や連携機能の省略)
- サポートが限定的(電話対応なし
そのため、一人社長のように従業員数が少ない状況では無料プランでコストを極小化できるメリットがある一方で、将来的に「従業員数増・機能拡張・法令改正対応」の必要が生じた際に、別プランまたは別ソフトへの移行が必要になる可能性があります。
人事部として使う場合も、運用の手間・サポートの限界・将来の拡張性まで見据えて検討することが賢明です。
つまり「無料で使える給与計算ソフトはあるが、その無料状態が永続的に保証されるわけではない」というのが実情です。